感覚運動科学の実践
感覚運動科学の現場応用にフォーカスした講座です。当講座で学ぶ内容は痛み・不調の改善、姿勢・動作の改善、スポーツパフォーマンスの向上まで、幅広く活用することができます。(配信予定頻度:2本/月)
サンプル動画
体幹トレーニングの再定義と実践①
体幹トレーニングの目的や方法をエビデンスを基に再定義をした後に、実際のトレーニング法をご紹介します。全3回シリーズの第1回目となる今回は従来の体幹トレーニングの問題点と代替策、そしていくつかのトレーニング例をお伝えします。
配信済のコンテンツ
-

感覚運動科学を活かした慢性障害へのアプローチ: ハムストリングスの肉離れ①
感覚運動科学の実践0:56:23
感覚運動科学の観点から慢性障害へのアプローチを学ぶ講座です。今回はハムストリングスの肉離れに着目します。①では感覚統合の問題や、中枢神経の機能低下が障害の原因となるメカニズムを掘り下げ、②では現場で活用できるアプローチ法をご紹介します。
-

感覚運動科学を活かした慢性障害へのアプローチ: 足関節不安定症②
感覚運動科学の実践0:51:25
感覚運動科学の観点から慢性障害へのアプローチを学ぶ講座です。今回は足関節不安定症に着目します。①では感覚統合の問題や、中枢神経の機能低下が障害の原因となるメカニズムを掘り下げ、②では現場で活用できるアプローチ法をご紹介します。
-

感覚運動科学を活かした慢性障害へのアプローチ: 足関節不安定症①
感覚運動科学の実践0:52:51
感覚運動科学の観点から慢性障害へのアプローチを学ぶ講座です。今回は足関節不安定症に着目します。①では感覚統合の問題や、中枢神経の機能低下が障害の原因となるメカニズムを掘り下げ、②では現場で活用できるアプローチ法をご紹介します。
-
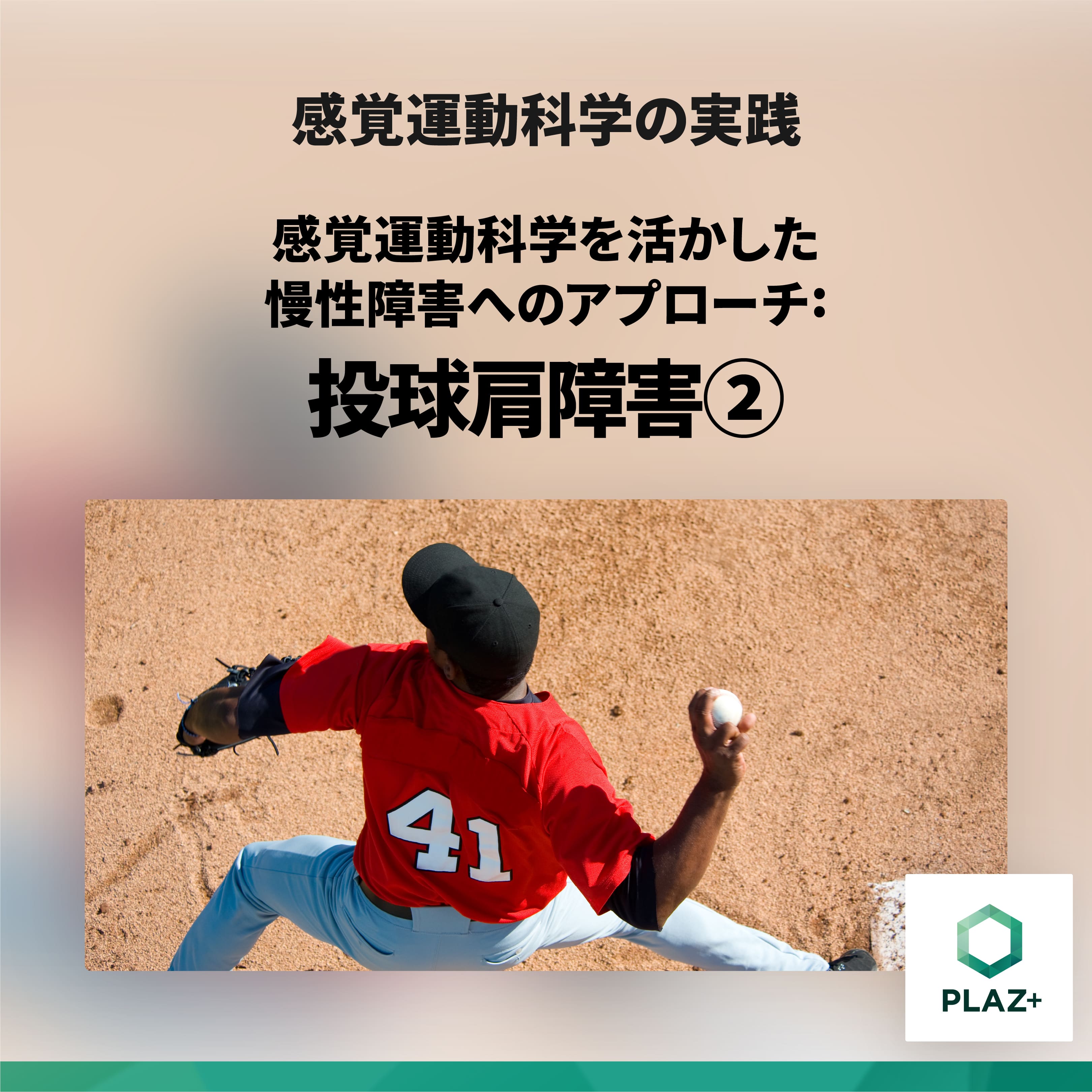
感覚運動科学を活かした慢性障害へのアプローチ: 投球肩障害②
感覚運動科学の実践0:51:27
感覚運動科学の観点から慢性障害へのアプローチを学ぶ講座です。今回は投球肩障害に着目します。①では体性感覚・視覚・前庭覚の統合不全や、中枢神経の機能低下が障害の原因となるメカニズムを掘り下げ、②では現場で活用できるアプローチ法をご紹介します。
-
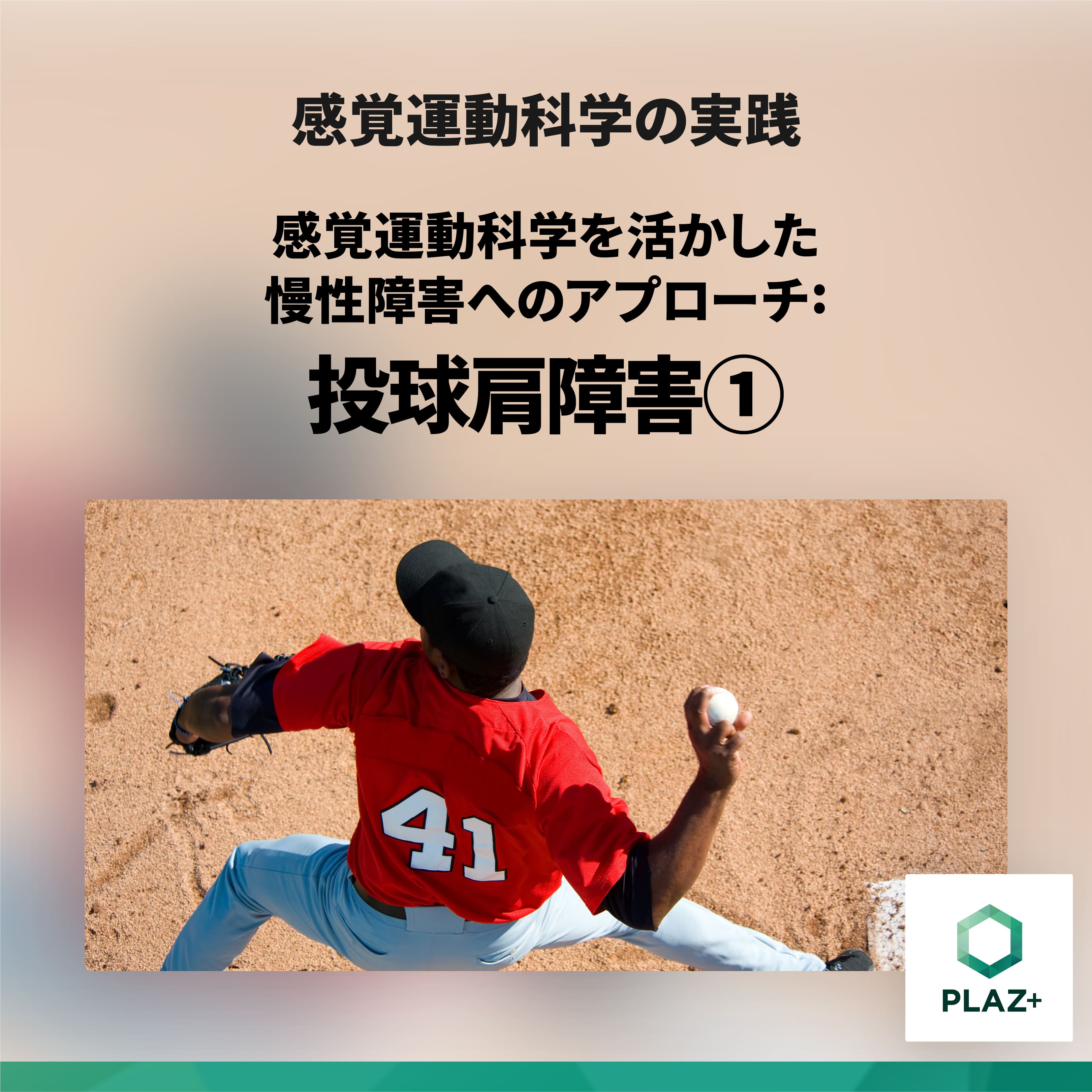
感覚運動科学を活かした慢性障害へのアプローチ: 投球肩障害①
感覚運動科学の実践0:59:45
感覚運動科学の観点から慢性障害へのアプローチを学ぶ講座です。今回は投球肩障害に着目します。①では体性感覚・視覚・前庭覚の統合不全や、中枢神経の機能低下が障害の原因となるメカニズムを掘り下げ、②では現場で活用できるアプローチ法をご紹介します。
-

感覚運動科学を活かした下肢の慢性障害へのアプローチ: 足底腱膜炎・シンスプリント・アキレス腱炎②
感覚運動科学の実践0:56:31
感覚運動科学の観点から慢性障害へのアプローチを学ぶ講座です。①では体性感覚・視覚・前庭覚の統合不全や、中枢神経の機能低下が慢性障害の原因となるメカニズムを掘り下げ、②では現場で活用できるアプローチ法をご紹介します。
-

感覚運動科学を活かした慢性障害へのアプローチ: 足底腱膜炎・シンスプリント・アキレス腱炎①
感覚運動科学の実践0:54:56
感覚運動科学の観点から慢性障害へのアプローチを学ぶ講座です。①では体性感覚・視覚・前庭覚の統合不全や、中枢神経の機能低下が慢性障害の原因となるメカニズムを掘り下げ、②では現場で活用できるアプローチ法をご紹介します。
-

感覚運動科学とピラティス②
感覚運動科学の実践1:00:35
感覚運動科学の観点からピラティスの活用法を学ぶ講座です。「ピラティスが上手くなるための指導」ではなく「心身の問題を解決するための指導」を実現するにはどのようなアプローチが必要になるのでしょう。②では前回の内容を基に、様々な目的に応じたプログラムや指導法をご紹介します。
-

感覚運動科学とピラティス①
感覚運動科学の実践1:09:28
感覚運動科学の観点からピラティスの活用法を学ぶ講座です。「ピラティスが上手くなるための指導」ではなく「心身の問題を解決するための指導」を実現するにはどのようなアプローチが必要になるのでしょう。①ではピラティスをはじめとしたボディワークが感覚運動系へ与える影響を掘り下げ、ピラティスの最適な活用法を考察します。
-

姿勢制御機能の評価と改善法 ②
感覚運動科学の実践0:56:00
感覚運動科学の観点から姿勢制御機能を掘り下げる講座です。姿勢制御機能を「静的姿勢保持」「外乱負荷応答」「随意運動」に分類し、各機能の評価と改善法をご紹介します。②では主にエクササイズを用いた姿勢制御機能の改善法にフォーカスしてお伝えします。
-

姿勢制御機能の評価と改善法 ①
感覚運動科学の実践0:51:49
感覚運動科学の観点から姿勢制御機能を掘り下げる講座です。姿勢制御機能を「静的姿勢保持」「外乱負荷応答」「随意運動」に分類し、各機能の評価と改善法をご紹介します。①では姿勢制御機能の科学的背景と評価法にフォーカスしてお伝えします。
-
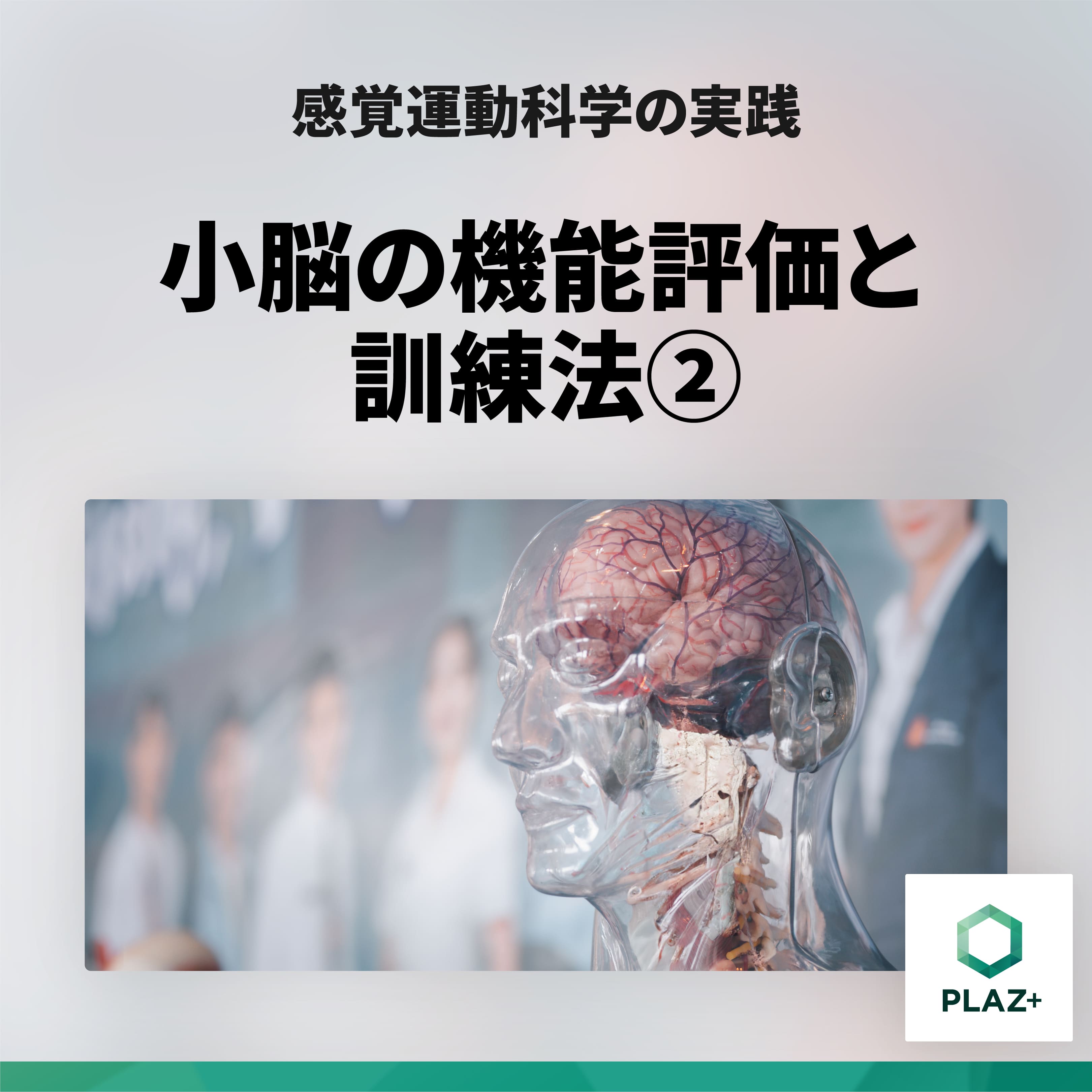
小脳の機能評価と訓練法②
感覚運動科学の実践0:40:36
感覚運動科学の観点から小脳へのアプローチを学ぶ講座です。「器用さがない」「運動が苦手」「ターゲットを正確に捕らえられない」など様々な問題に対応するための知識を身に付けることができます。②では小脳の訓練法について掘り下げていきます。
配信予定のコンテンツ
-
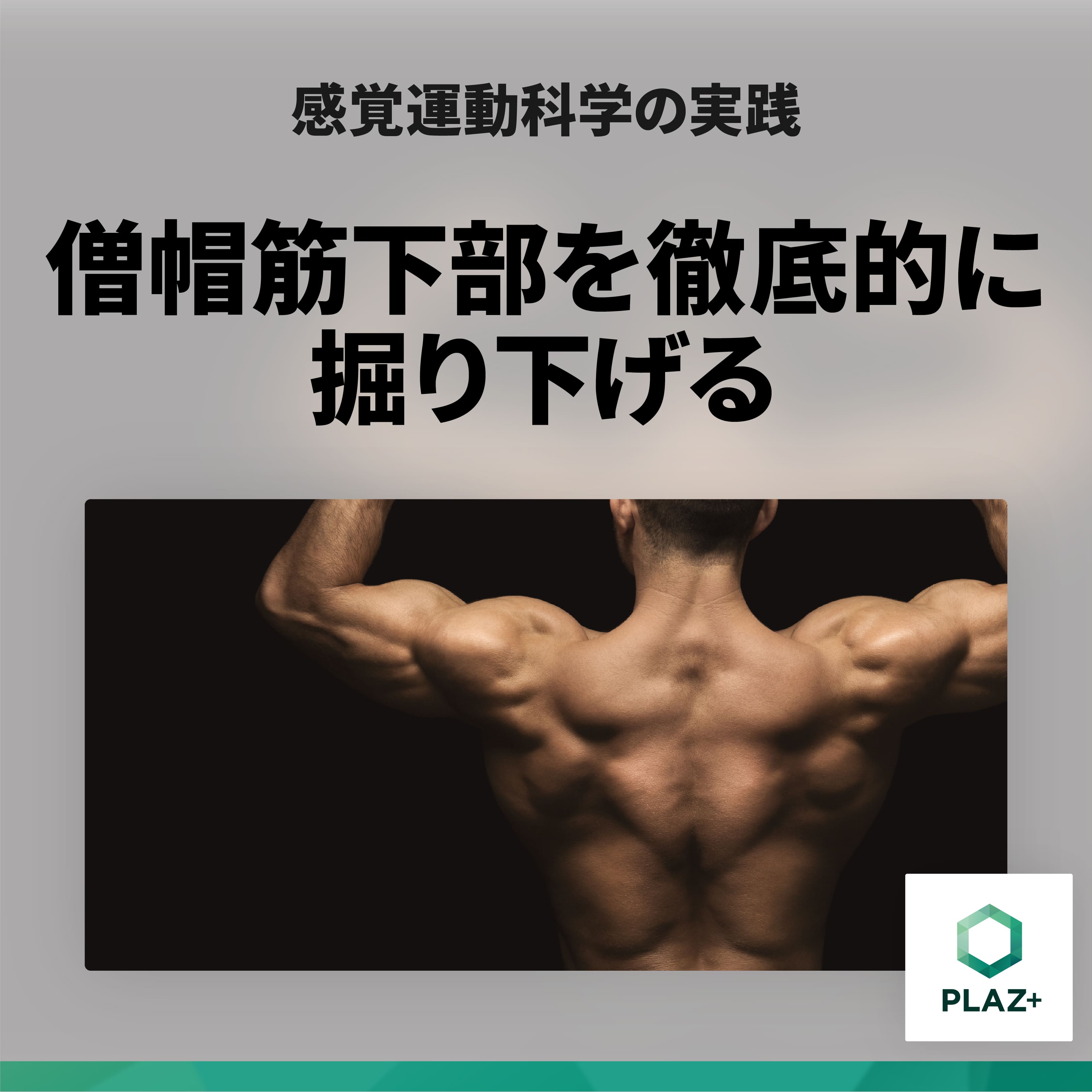
-

Brain is Target Oriented - ターゲットを用いた運動指導①
感覚運動科学の実践本講座では感覚運動科学の観点から「なぜ、ターゲットを用いた運動指導が効果的なのか?」を掘り下げます。スクワット、腕立て伏せなど通常の運動に標的を加えることで脳と体にどんな変化が起きるのでしょうか?明日からの運動指導に即時活用できる内容となっております。
-

Brain is Target Oriented - ターゲットを用いた運動指導②
感覚運動科学の実践本講座では感覚運動科学の観点から「なぜ、ターゲットを用いた運動指導が効果的なのか?」を掘り下げます。スクワット、腕立て伏せなど通常の運動に標的を加えることで脳と体にどんな変化が起きるのでしょうか?明日からの運動指導に即時活用できる内容となっております。
