エビデンスから紐解く感覚運動科学
教育者と臨床家の両天秤で活躍する阿部さゆりによる、エビデンス(科学的根拠)を基に感覚運動科学を考察する講座です。抽象的な解釈に陥りやすい感覚運動系へのアプローチを明確に理解・応用するための知識が手に入ります。(配信予定頻度:2回/月)
サンプル動画
自律神経と感覚運動①
日々の生活の中で揺らぎ動く自律神経活動。これが乱れたときに、私たちの感覚や運動はどう動かされるのか?健康的に活動するために、どのような自律神経活動が望ましいのか?エビデンスを紐解いてみましょう。
配信済のコンテンツ
-
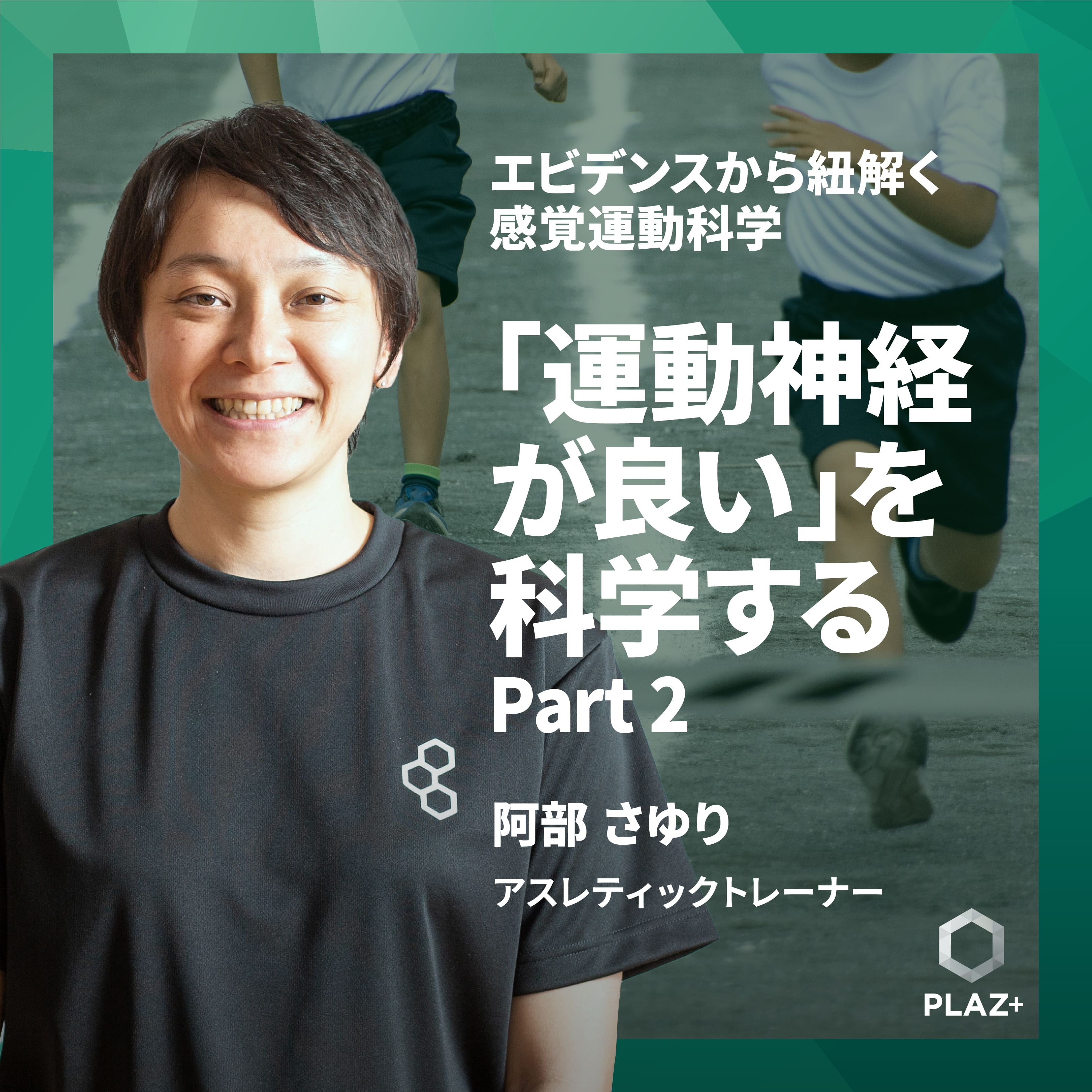
「運動神経が良い」を科学する Part 2
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:33:50
『運動神経が良い』とは、具体的にどのような状態や能力を指すのでしょうか?そしてそれらの要素を先天的なものなのでしょうか、後天的に効果的に伸ばすことはできるのでしょうか?科学的なデータから想像と創造を膨らませてみましょう。
-

「運動神経が良い」を科学する Part 1
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:38:02
『運動神経が良い』とは、具体的にどのような状態や能力を指すのでしょうか?そしてそれらの要素を先天的なものなのでしょうか、後天的に効果的に伸ばすことはできるのでしょうか?科学的なデータから想像と創造を膨らませてみましょう。
-

脊柱側弯と歩行
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:45:50
脊柱側弯というと『異常なもの』というイメージが強いですが、実はデータによれば右への側弯はある程度「正常変異」なのではないかという見方もできます。私たちの脊柱を右に曲げるチカラの正体はなんのか?どう介入できるのか?脊柱が左に側弯する場合、潜んでいる要素はなんなのか?最新エビデンスから紐解いてみましょう。
-

-

Got Peers? 「仲間がいる」ことの科学的意義
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:10:47
ひとりでダメなら、誰かと、みんなで!サイエンスが紐解く「仲間」の持つチカラと意義について考察してみましょう。
-

「習慣」のチカラ
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:11:20
悪習慣を打破し、良習慣を築きたい。そのための一歩はまず習慣形成のプロセスやその影響力に関する知識をつけることからです。エビデンスを掘り下げ、学んでみましょう。
-

オーラルヘルス(口腔衛生)の考察
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:15:48
講師が資料スライドと口頭で「歯石」と表現しているものは「歯垢(しこう)」の間違いです。誤解を生む表現となり大変恐縮ですが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ただ「歯磨きをしていればいい」だけじゃない!『歯や口の健康』と『運動』やその他さまざまなヒトの機能との繋がりをエビデンスから紐解いてみましょう。
-

Virtual Realityと感覚運動 Part 2
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:22:53
科学の発展目覚ましい近年、仮想現実(Virtual Reality: VR)をリハビリテーションに用いる試みも増えてきました。エビデンスの最先端をレビューし、臨床実践への応用について考えを膨らませてみましょう。
-

Virtual Realityと感覚運動
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:15:56
科学の発展目覚ましい近年、仮想現実(Virtual Reality: VR)をリハビリテーションに用いる試みも増えてきました。エビデンスの最先端をレビューし、臨床実践への応用について考えを膨らませてみましょう。
-
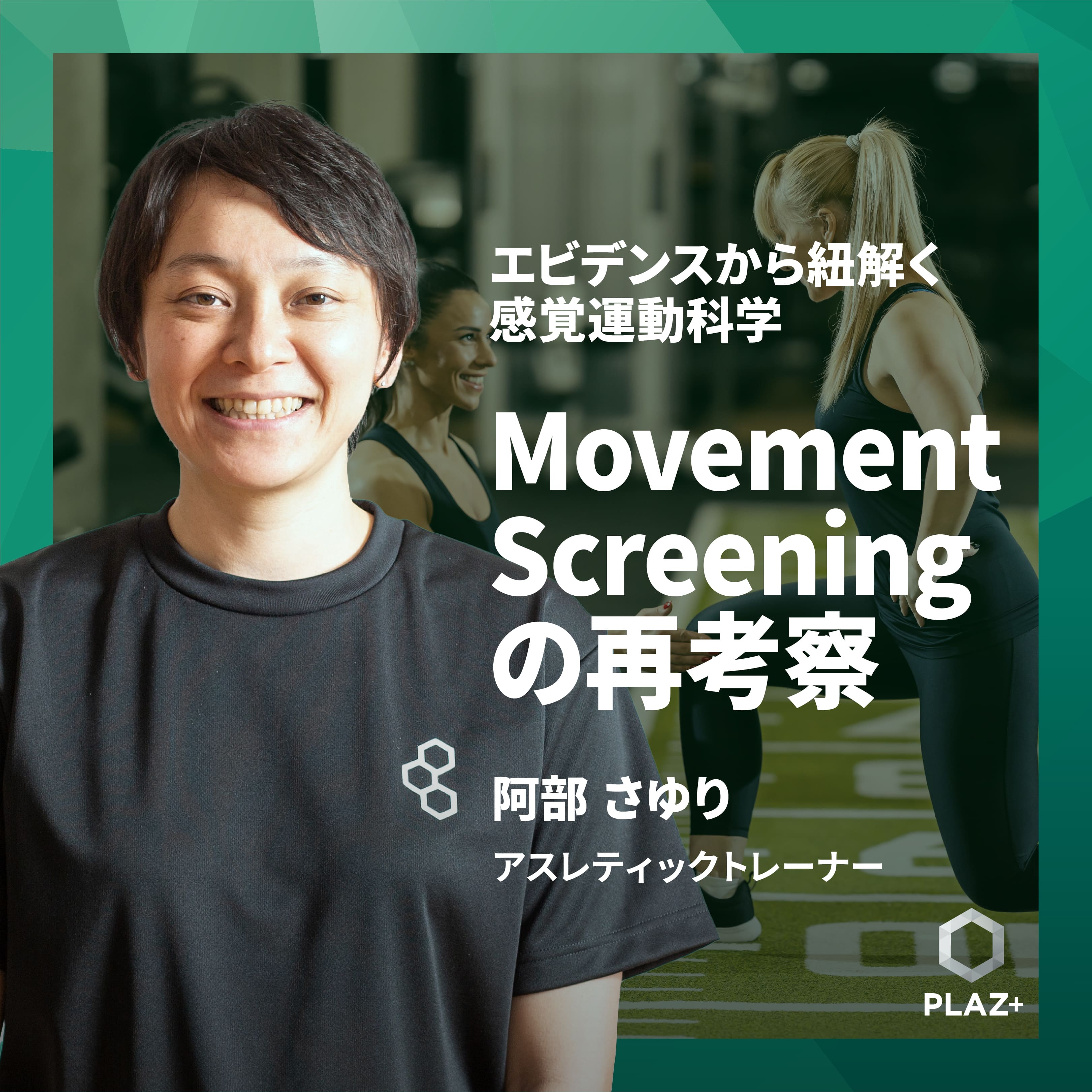
Movement Screening の再考察
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:29:36
動作を障害予防のスクリーニングに用いる、という文化がスポーツ界で一般的となって久しいですが、我々はこのツールにより本当は何を推し量っているのでしょうか?エビデンスと共に紐解いてみましょう。
-

骨盤底のサイエンス
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:33:05
ともすればWomen's Healthの専門領域と思われがちな「骨盤底」という部位、苦手意識を抱く人も多いのではないでしょうか?全てのヘルスケア・フィットネスの専門家が知っておくべき骨盤底の奥に潜むサイエンスと臨床実践について学んでいきましょう。
-

肩甲骨のサイエンス
エビデンスから紐解く感覚運動科学1:33:22
胸郭にただ浮いているだけ?…いえいえ、そんなことはありません。身体パフォーマンスにおける、肩甲骨の果たすべき役割とはなんでしょう?様々なエビデンスから考察してみましょう。
配信予定のコンテンツ
配信予定のコンテンツはありません。
